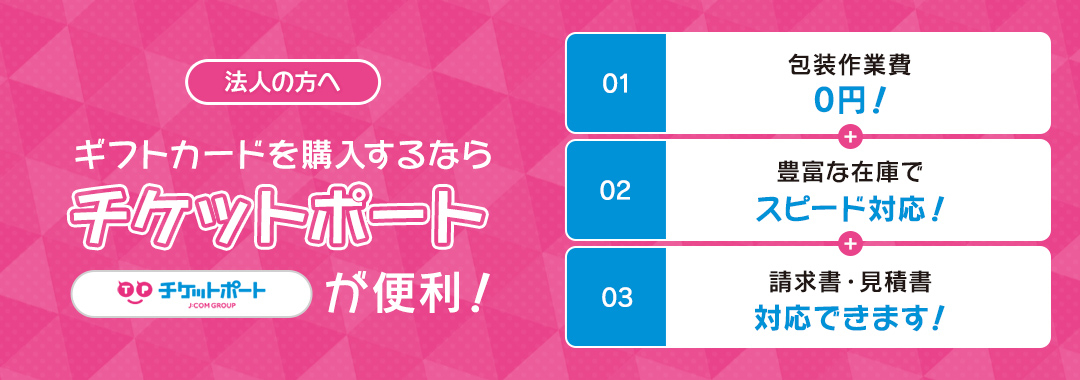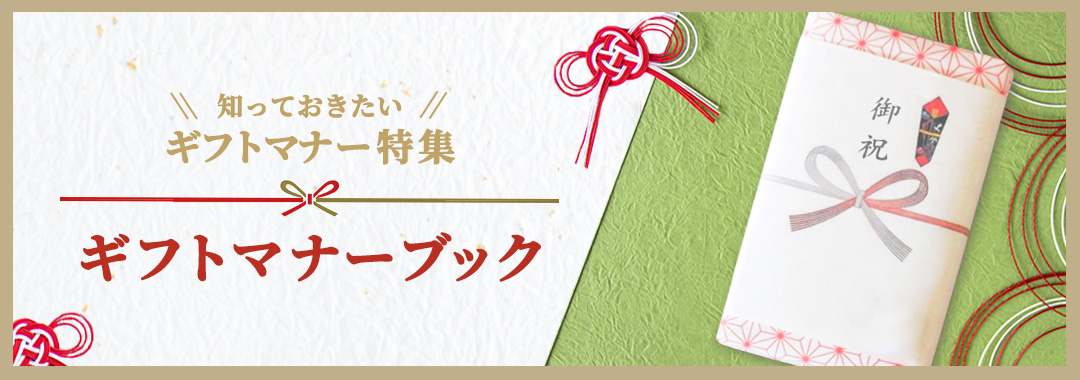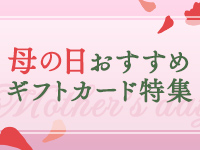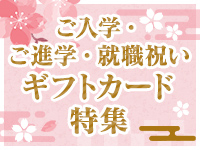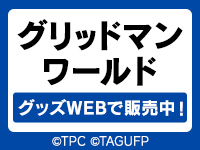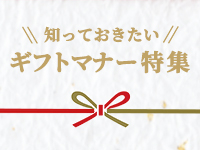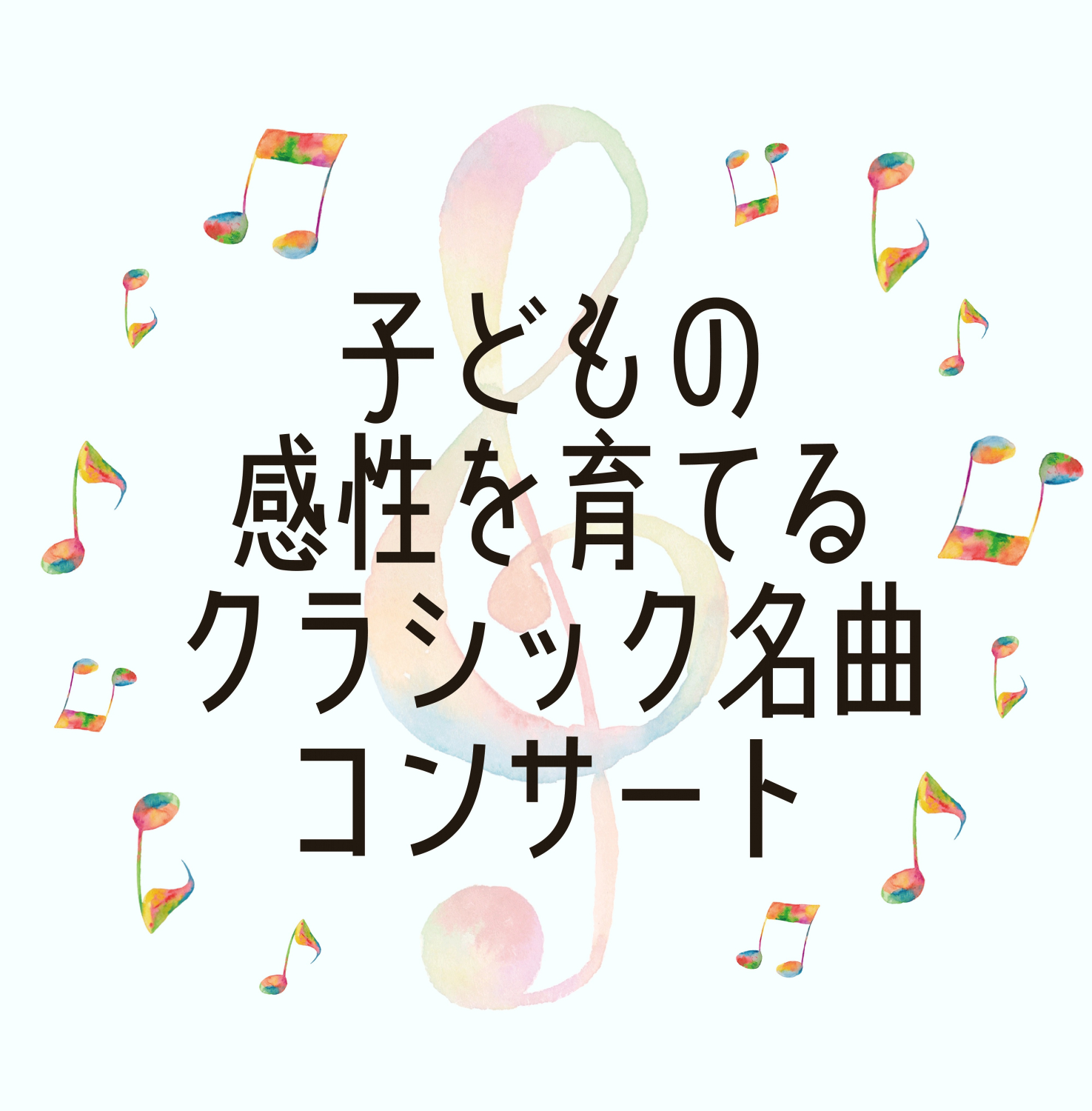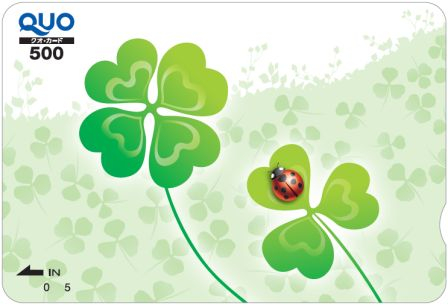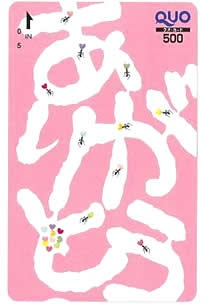重要なお知らせ
- 2024.4.15
- 重要【チケットポート】ゴールデンウィーク休業期間のお知らせ
- 2024.3.18
- 重要【チケットポート】アサヒスーパードライ鮮度ギフトカードの価格改定のお知らせ
- 2024.2.2
- 重要【お詫び】グリッドマンワールド ご注文多数による発送遅延のお知らせ
セレクション

チケットポート
チケットポート各店舗では各種ギフトカードや映画券、展覧会の入場券を販売しております。 対面販売ならではのきめ細かいサービスで長くお客様に支持されています。また、豊富な在庫で急なご入用にも対応でき、喜ばれております。

グリッドマンワールド
グリッドマンワールド展で大人気だったアイテムが再び登場! グリッドマンワールドの世界観をお楽しみください。
公演のおすすめ商品
- 発売開始:2024年4月20日(土)
- 公演日:2024年7月20日(土) 開演17:30
- 公演会場:和光市民文化センターサンアゼリア大ホール
- 発売開始:2024年3月23日(土)
- 公演日:2024年4月21日(日) 開演13:00
- 公演会場:渋谷区文化総合センター大和田さくらホール
- 発売開始:2024年3月23日(土)
- 公演日:2024年4月21日(日) 開演17:30
- 公演会場:渋谷区文化総合センター大和田さくらホール
- 発売開始:2024年3月15日(金)
- 公演日:2024年5月5日(日) 開演16:00
- 公演会場:東京芸術劇場コンサートホール
- 発売開始:2024年3月8日(金)
- 公演日:2024年9月1日(日) 開演15:30
- 公演会場:新日本造機ホール(呉市民ホール)
- 発売開始:2024年3月8日(金)
- 公演日:2024年10月4日(金) 開演19:00
- 公演会場:Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
- 発売開始:2024年7月6日(土)
- 公演日:2024年10月19日(土) 開演17:30
- 公演会場:市原市市民会館大ホール
- 発売開始:2024年5月6日(月)
- 公演日:2024年7月14日(日) 開演14:00
- 公演会場:高崎芸術劇場大劇場
QUOカードのおすすめ商品
ギフトカードのおすすめ商品
JCBギフトカード
プレゼントに最適!JCBギフトカードで、笑顔を届けよう
1,000円券/5,000円券
500円券/1,000円券/2,000円券/3,000円券/5,000円券
5,500円券
5,500円券
3,000円券
3,500円券
3,000円券
5,000円券